国民年金
国民年金制度は、歳をとったり、病気や怪我で障害者となったり、一家の働き手を失った時など、年金により経済的な援助をするため、すべての国民が助け合っていくという相互扶助の制度で、国が責任を持って運営しています。
国民年金に加入する方
日本に居住する20歳以上60歳未満のすべてが対象(強制加入)です。会社員の人は厚生年金等に加入することで国民年金にも加入していることになります。このほかにも、任意加入や特例任意加入できる場合もあります。詳しくは、役場住民生活課へお問い合わせください。
保険料
国民年金の保険料は、性別、年齢、所得又は、地域などに関係なく全国一律です。
令和7年度保険料額
定額保険料 月額 17,510円
付加保険料 月額 400円
保険料の納付
国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。
口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替をご利用される方は、住民生活課またはお近くの年金事務所、金融機関の窓口で手続きをお願いします。
クレジットカード納付(継続納付)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法です。希望する場合は、住民生活課または年金事務所にお申込が必要です。詳しくは、住民生活課、お近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。
納付書
納付書を使用し、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。なお、お手元に納付書がないときは、年金事務所までご連絡ください。
スマートフォンやパソコン
納付書に記載されている番号を使用しPey-easy(ペイジー)で、お手持ちのスマートフォンやパソコンから、自宅や外出先で、夜間や休日でも納付できます。
国民年金のオンラインサービスについて
日本年金機構の「ねんきんネット」に登録することで、スマートフォンやパソコンから、年金記録確認ができます。また、マイナポータルと連携することで個人向け通知書の電子送付サービス(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)・公的年金等の源泉徴収票)を受ける手続き等が可能になります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンで国民年金関係の電子申請が可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページで確認ができます。
国民年金の保険料は全額社会保険料控除の対象
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年10月下旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
| 手続きの種類 | 届出に必要なもの |
|---|---|
|
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき (扶養配偶者がいる場合は合わせて届け出をしてください) |
年金手帳または、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの 退職年月日がわかるもの(離職票など) |
|
配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
本人・配偶者の年金手帳または、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの 扶養からはずれた年月日がわかるもの |
|
任意加入するとき (口座振替が原則となります。) |
年金手帳または、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの 預(貯)金通帳及び金融機関への届出印 |
|
付加保険料を納めたいとき (申出月からの開始となります。) |
年金手帳または、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
|
海外に居住することになった時
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
保険料の納付方法
任意加入には手続きが必要です。
| どのような人 | 手続き窓口 |
| 今現在御杖村に居住されていて、これから海外に転居する人 |
住民生活課で手続きが出来ます。 |
| 現在海外に居住されている人 |
日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または、市区町村窓口 |
保険料の納付方法
保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
詳しくは、住民生活課または年金事務所へお問い合わせください。
帰国した時の手続き
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票への登録)、国民年金は強制加入被保険者となります。強制加入には手続きが必要ですので、転入した市区町村役場で手続きを行ってください。
一時帰国の時
一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票への登録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要になります。
給付の条件
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
障害基礎年金
- 一定の給付用件を満たしている方で、国民年金に加入されている方や老齢基礎年金を受ける資格のある方が、 障害の程度が国民年金に定める1級又は2級の障害となったとき。(注意:障害者手帳の障害等級とは異なります)
- 20歳前の初診日で障害の状態(国民年金の定める1級または2級)になったときは20歳に達してから支給。
遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある妻、または子に支給されます。 子とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子供をいいます。なお、障害のある方は20歳未満です。
受給するには、次の条件があります。
- 死亡日の前々月までの加入期間に、保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日の前々月までの1年間に滞納がないこと。(平成18年3月31日までの死亡に限る。)
寡婦年金
第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでのあいだ支給。夫が「障害基礎年金」を受給している場合を除く。
付加年金
第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときその遺族に支給。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
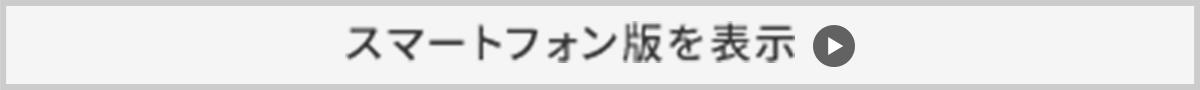







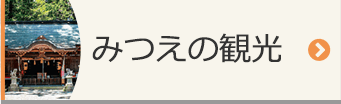
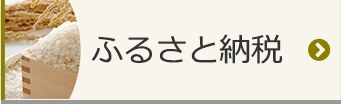
更新日:2024年06月05日